夏が近づくと、スーパーやコンビニに「今年は土用の丑の日は〇日です」のポスターを見かけると
「鰻の季節がやってきた」と思う方いるのではないでしょうか?
今年2025年の土用の丑の日は7月19日と7月31日と2回あります。
そもそも、”土用の丑の日”って何でしょう?
なんで、“丑”の日に“鰻”?
なんとなく夏の風物詩のように受け止めているけど、改めて考えてみると”土用の丑の日”って何だろうって思い・・・・・・。
今回は、そんな「土用の丑の日」についてまとめてみました。
土用の丑の日って何?

土用の丑の日は鰻=夏のイメージが思い浮かびませんか?
筆者は、”土用の丑の日は夏のイメージ”しかない思っていましたが・・実は「土用」は年に4回と、季節の変わり目にあるんです。これには筆者もびっくり!!
暦の上で「立春・立夏・立秋・立冬」それぞれの直前の約18日間の間であり、春夏秋冬に”土用”があること、今のところ知っているのは「夏の土用」。筆者の中では、夏に鰻を食べるからという単純な理由でもあります。
その中でも、「十二支」でいう”丑の日”にあたる日を「土用の丑の日」と呼ぶ事にも驚きでした。まさか鰻の日に十二支が関わってくるとは・・・・・・。
十二支は日付に割り振られる12日ごとに巡ってくるので、土用の期間中に丑の日が2回くる年もあるんです。カレンダーを見てみると、横に小さく干支が書かれていますね\( ‘ω’)/
2025年の土用の丑の日
- 立冬 1/17~2/2 (1月20日・2月1日)
- 立春 4/17~5/4 (4月26日)
- 立夏 7/19~8/8 (7月19・7月31日)
- 立秋 10/20~11/16(10月23日・11月4日)
ちなみに来年の土用の丑の日は、2026年7月26日です。
忘れずにメモしときましょう(笑)
鰻の栄養は夏の暑さに備えあれば憂いなし
鰻って、実はとっても栄養たっぷりなんです。夏の暑さで体が疲れた時にピッタリの食べ物なんです。
鰻に含まれる栄養素とその働き
・ビタミンA
- 効果:目の健康を守る。皮膚や粘膜を丈夫に保つ・免疫力アップ
- 補足:夏の紫外線やエアコンの乾燥で、目や肌はダメージを受けがちです。ビタミンAは粘膜の保護に強く、風邪や感染症の予防にも繋がります。
・ビタミンB1
- 効果:糖質のエネルギー変換を助ける・疲労回復効果がある。
- 補足:ご飯やパンなどの主食に含まれる糖質を、効率よくエネルギーに変えて、夏バテや体の怠さ、食欲不振の回復に◎。
・ビタミンD
- 効果:カルシウムの吸収を助ける・骨の強化
- 補足:ビタミンDは“日光のビタミン”とも言われていますが、室内にこもりがちな夏にはビタミンDが不足がち。鰻でビタミンDを補えるのは嬉しいポイントです!
・ビタミンE
- 効果:血行促進・細胞の老化を防ぐ抗酸化作用。
- 補足:冷房で血流が悪くなる夏の冷えに効果的。体のさびつきを防いで、アンチエイジングにも期待できます。
・DHA
- 効果:脳の働きをサポート・記憶力や集中力アップ。
- 補足:青魚に多く含まれ、特に育ち盛りの子供や忙しい大人にもぴったり!頭の回転を良くしたい時に◎。
・EPA
- 効果:血液サラサラ効果・中性脂肪の低下、心臓血管の健康を守る。
- 補足:動脈硬化や高血圧の予防にも繋がる、心強い脂肪酸です。
鰻は夏を乗り切った、昔の人が選んだ「鰻」という知恵だった?

冷房や冷たい飲み物があふれている今の時代とは違い、昔の人たちにとって夏はまさに試練の季節!!
寝苦しい夜、照り続ける日差し、食欲も落ちてしまう日々。(現代でもそんな変わらないかも)
そんな夏をどう乗り切るか、というのは長い間の課題と生活の知恵にかかっていました。
そこで頼りにされていたのが、スタミナたっぷりの鰻。
脂がのっていて、しかも白身魚だから消化にも優しい。弱った体にもスッと入る“滋養食”として、昔から親しまれてきました。
そしてこの“鰻を夏に食べる習慣”を広めた立役者が大河ドラマ【べらぼう】にも出ていた「平賀源内(ひらがげんない)」という江戸時代の学者です。
ある鰻屋さんが、「夏は鰻が売れなくて困ってる」と相談に来た時、彼が「”丑の日には“う”のつくモノを食べると良い”」と書いて店主に渡し、店内に貼ったところ、このアイデアが見事に当たりお店は大繁盛!!
そこから、「土用の丑の日に鰻を食べる」という文化が広まったと言われています。
もちろん、これは宣伝の一部だったのかもしれませんが、当時の人々は実際に鰻を食べて元気になったからこそ、風習として定着したのかもしれませんね。理屈だけじゃなく、「体が喜ぶ感覚」って今の私たちよりも、昔の人の方がよっぽど敏感だったのかもしれませんね。
東洋の考え方では、”土用”は体調を整える期間
東洋医学や陰陽五行の考え方では、「土用」は“土の気”が高まる期間とされていて、「五臓六腑のバランスが崩れやすい=デリケートな期間」でもあるようです。
特に夏の土用は、湿度と気温の高さから消化器系が弱りやすく「脾胃(ひい)=胃腸」を労わることが大切とされてきました。
だからこそ、栄養豊富で消化にも良く、スタミナがつく鰻がピッタリだったんですね。
当時は、「ビタミンが・・」「DHAが・・」なんて難しいことは知られていませんが、経験で「鰻を食べたら元気が出る」「夏バテが治る」と実感していたのかもしれませんね。
奈良時代「万葉集」にも登場する鰻
古くは奈良時代の「万葉集」にも登場している鰻の記述が残されています。
有名なのが、大伴家持の歌です。
石麿盧に 吾物申す 夏瘦せに 良しというものぞ 鰻取り食せ
(いわしろに わがものもうす なつやせに よしというのぞ うなぎとりめせ)
【大伴家持 巻十六-三八五三】
「夏バテしてるなら、鰻食べて元気になって」という鰻を勧める歌なんでしょうね。
1300年以上の前から「鰻=夏の元気の源」として意識されていたことがうかがえます。
奈良県のホームページにも詳しく解説しております。
鰻が食べられないときは”う”の付く食べ物でもOK!!
今の物価高で、鰻の値段が高くなったことや、資源の保護を考えて「鰻以外を食べる」という選択肢を取る人も増えてきています。
昔から「丑の日には“う”の付く食べ物を食べると良い」という言い伝えがあり、それに伴って鰻以外の“う”のメニューを楽しむ人も。
たとえば・・・
- 梅干し:クエン酸で疲労回復、食中毒予防にも
- うどん:さっぱりして、消化にも良い
- 瓜(うり)類:水分が多く、体の熱を冷ます
- 牛肉(うし):ボリュームで元気をチャージ!!
よく、鰻と梅干は【悪い食べ合わせ】って言われてきました。筆者も、小さい頃よく「鰻と梅干し番組一緒に食べるもんじゃない」と言われてきました。ですが、梅干に含まれるクエン酸の酸味が胃酸分泌を促し、脂の多い鰻でも胃もたれせず逆に消化促進される組み合わせになっているんですね。
家庭の食卓でも、鰻ではなく自分のオリジナルの「丑の日ごはん」を楽しむのもいいのでは( ` -´ )b
まとめ 〜“鰻の日”に込められた、昔からの知恵~
土用の丑の日に鰻を食べる――。
それは単なる風習ではなく、「暑さに負けないように」「体を大事にして、元気に夏を越えよう」という、昔の人たちの知恵と想いの積み重ねなんですね。
奈良時代にはすでに「夏痩せには鰻がいい」と詠まれ、
江戸時代には平賀源内のユニークな発想で広まり、
そして現代にもこうして、夏の風物詩として受け継がれています。
でも、無理して高価な鰻を食べなくてもいいと思うんです。
“う”のつく食べ物や、体にやさしいものを選んで、
「今日くらいは自分をいたわってあげよう」って思えることが大切。
鰻でも、うどんでも、梅干しでも。
その一口に込めるのは、栄養と、やさしさと、ちょっとした夏のおまじない。
今年の丑の日は、自分や家族の体を気遣ってみませんか?
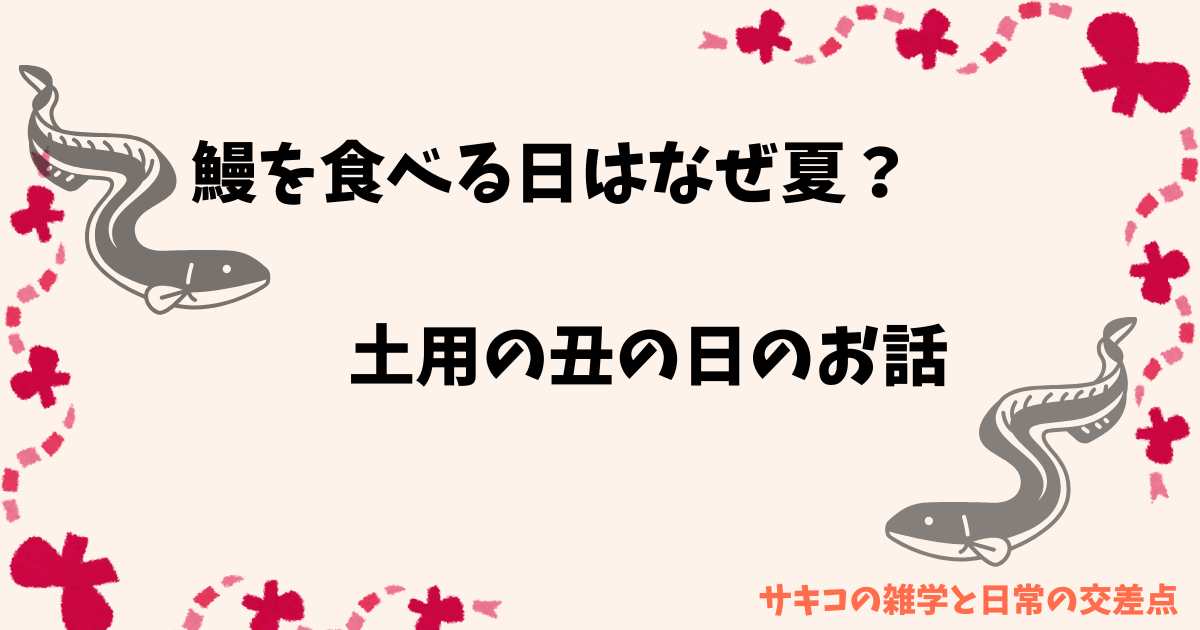
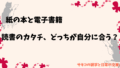
コメント